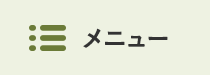痛みをコントロールする「下降性抑制系」とは?
こんにちは!今回は、「痛みを抑える仕組み」のひとつである下降性抑制系についてお話しします。
私たちの体は、ケガや病気をすると「痛み」を感じます。しかし、状況によっては「痛みを感じにくくなる」こともありますよね。例えば、スポーツ中にケガをしても、その瞬間は痛みをあまり感じず、試合が終わってから気づくことがあります。これは、脳が「痛みを抑える指令」を出しているからです。
この仕組みの中心的な役割を果たしているのが、下降性抑制系(Descending Inhibitory System)です。
下降性抑制系とは?
下降性抑制系とは、中脳の腹側被蓋野から脊髄後角に向かって「痛みを抑える信号」を送る神経回路です。この回路が働くことで、痛みが軽減されます。
具体的には、脊髄の後角(痛みの情報が伝わる部位)に対して、脳幹から抑制の信号が送られ、痛みの伝達をブロックします。
どのようなときに働くの?
• スポーツや戦闘時など「すぐに逃げたり戦ったりしなければならない場面」
• ストレスが強い状況(ストレス誘発性鎮痛)
• 鍼灸やマッサージなどの刺激
• モルヒネなどの鎮痛薬の作用
下降性抑制系を活性化する方法
1. 鍼灸治療
鍼灸の刺激は、中脳中心灰白質(PAG)を活性化し、エンドルフィン(脳内モルヒネ)を放出させます。これにより、下降性抑制系が強化され、鎮痛効果が期待できます。
2. 運動
ランニングやウォーキングなどの有酸素運動は、エンドルフィンを増やし、痛みを軽減します。
3. 深呼吸・瞑想
リラックスすると、ストレスホルモンが減少し、下降性抑制系が働きやすくなります。
4. 温熱療法(お風呂や温湿布)
温めることで血流が改善し、神経の興奮が抑えられ、痛みが和らぎます。
まとめ
• 下降性抑制系は、「痛みを抑えるブレーキ」のような働きをする神経回路
• 中脳中心灰白質(PAG)→ 大縫線核(NRM)→ 青斑核(LC)の経路で痛みを抑制
• 鍼灸・運動・リラックス法などで活性化できる
痛みをコントロールするためには、この「下降性抑制系」を上手に働かせることが大切です。
慢性的な痛みやストレスを感じている方は、鍼灸やリラックス法を取り入れてみるのもおすすめです!
ストレスが続くと下降性抑制系の働きが悪くなることがわかっています。
当院のトリガーポイント療法は自律神経を調整し、ストレスを軽減することもできます。トリガーポイント療法で下降性抑制系を賦活させ、ストレスを軽減しましょう🙇♂️
最後までお読みいただき、ありがとうございました!