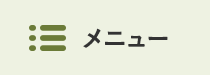当院のトリガーポイント鍼治療は、自律神経のバランスを整え、副交感神経を優位にする効果があります。
副交感神経が優位になることで、白血球の一種であるリンパ球が増加します。
白血球は主に 顆粒球(好中球など)・リンパ球・単球 の3種類に分類されます。自律神経と白血球の関係は以下のようになります:
• 交感神経が優位:顆粒球が増加し、リンパ球が減少
• 副交感神経が優位:リンパ球が増加し、顆粒球が減少
そのため、副交感神経が優位になると リンパ球の割合が増え、全体の白血球数がわずかに増加することもある ものの、顆粒球の減少によって総白血球数はあまり変わらない場合もあります。
また、副交感神経優位の状態は 免疫の調整や炎症の抑制 に関与すると考えられています。
リンパ球は、白血球の一種であり、免疫機能を担う主要な細胞 です。リンパ球には主に以下の3つの種類があります。
1. T細胞(Tリンパ球)
役割: 獲得免疫(特異的免疫)の中心的な働きをする
特徴:
• 胸腺で成熟する
• 病原体を直接攻撃したり、免疫応答を調整する
• ヘルパーT細胞:B細胞や他の免疫細胞を活性化
• キラーT細胞:ウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃・破壊
• 制御性T細胞:過剰な免疫反応を抑制
2. B細胞(Bリンパ球)
役割: 抗体を産生し、体液性免疫を担当
特徴:
• 骨髄で成熟する
• 抗原を認識すると形質細胞に分化し、抗体(免疫グロブリン)を産生
• メモリーB細胞 は同じ病原体に再感染した際にすばやく抗体を作る
3. NK細胞(ナチュラルキラー細胞)
役割: 免疫監視機構として働き、ウイルス感染細胞やがん細胞を自然免疫的に排除
特徴:
• T細胞やB細胞と異なり、特定の抗原を認識せずに攻撃できる
• 免疫の第一線として、異常細胞を即座に破壊
リンパ球の割合とバランス
通常、血液中の白血球の 約20〜40% がリンパ球です。
• ストレスや交感神経優位 → リンパ球減少(顆粒球が増加)
• リラックスや副交感神経優位 → リンパ球増加
リンパ球の役割まとめ
• T細胞 → 細胞性免疫(ウイルス・がん対策、免疫調整)
• B細胞 → 体液性免疫(抗体を作る)
• NK細胞 → 免疫監視(異常細胞を即攻撃)
免疫のバランスを保つには、リンパ球と顆粒球の適切な比率が重要です。
顆粒球は、白血球の一種で、細胞質内に顆粒を持ち、主に自然免疫を担当する細胞 です。顆粒球には以下の3種類があります。
1. 好中球(Neutrophil)
役割: 細菌感染や炎症への最前線での対応
特徴:
• 白血球の 50〜70% を占める(最も多い)
• 細菌や異物を**貪食(飲み込んで消化)**する能力が高い
• 感染部位へ速やかに移動し、膿の主成分になる
増加する状況:
• 細菌感染(肺炎、敗血症など)
• 炎症(怪我、火傷、自己免疫疾患)
• 交感神経が優位な状態(ストレス、興奮時)
⸻
2. 好酸球(Eosinophil)
役割: 寄生虫やアレルギー反応への関与
特徴:
• 白血球の 1〜5% を占める
• 寄生虫感染(特に回虫、フィラリアなど)で増加
• アレルギー反応(花粉症・喘息など) に関与し、ヒスタミンを放出する
増加する状況:
• 寄生虫感染(回虫症、トキソプラズマ症など)
• アレルギー疾患(花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎)
• 好酸球性肺炎や膠原病 などの疾患
⸻
3. 好塩基球(Basophil)
役割: アレルギー反応や炎症の調整
特徴:
• 白血球の 1%未満(最も少ない)
• ヒスタミンやセロトニン を放出し、アレルギー反応を促進
• マスト細胞(肥満細胞) と似た働きを持つ(主に血液中に存在)
増加する状況:
• アレルギー反応(アナフィラキシーショックなど)
• 炎症性疾患(慢性骨髄性白血病など)
顆粒球が増えること自体は、体の防御反応として重要ですが、慢性的に増加すると問題になることがあります。
顆粒球が増えるメリット
• 細菌感染や炎症に素早く対応(特に好中球の増加)
• 傷ついた組織を修復するプロセスの一部
• 免疫システムが正常に働いている証拠(一時的な増加は正常な反応)
しかし、ストレスや慢性炎症で顆粒球が過剰に増えると問題が生じる ことがあります。
顆粒球が慢性的に増えるデメリット
1. 組織の損傷を引き起こす
• 顆粒球は活性酸素を放出し、細菌を攻撃しますが、これが過剰になると正常な細胞も傷つける。
• これが慢性炎症や組織の劣化(動脈硬化、胃炎など)の原因になる。
2. 免疫のバランスが崩れる
• 交感神経優位(ストレス状態) → 顆粒球が増加し、リンパ球が減少。
• リンパ球はウイルス感染やがん細胞を排除する働きを持つため、顆粒球が多すぎると免疫全体のバランスが崩れ、病気にかかりやすくなる。
3. 慢性疾患との関係
• 胃潰瘍・胃炎(ピロリ菌感染+ストレス)
• 動脈硬化(血管の慢性炎症)
• 自己免疫疾患(免疫の過剰反応)
• がんリスクの増加(リンパ球の減少により監視機能が低下)
⸻
結論
顆粒球の増加は感染症や炎症時には必要ですが、慢性的なストレスや炎症で増え続けることは望ましくない です。
特に交感神経が優位になりすぎると、顆粒球が過剰に増え、組織ダメージや免疫の乱れにつながります。
ストレス管理や副交感神経を優位にする習慣(深呼吸・睡眠・リラックス時間の確保など)が、免疫バランスを保つために重要 だと考えられます。


関連する記事
-
- 2025/03/30
- くしゃみが引き起こすギックリ腰のメカニズムとは?
-
- 2025/03/30
- なぜ保育士は手首を痛めやすいのか?共通する動作と予防法
-
- 2025/03/27
- 肩から指先までの痺れ〜簡単に治るかも
-
- 2025/03/23
- 変わりたいなら、変え続けよ〜皆さまの本気に向き合う